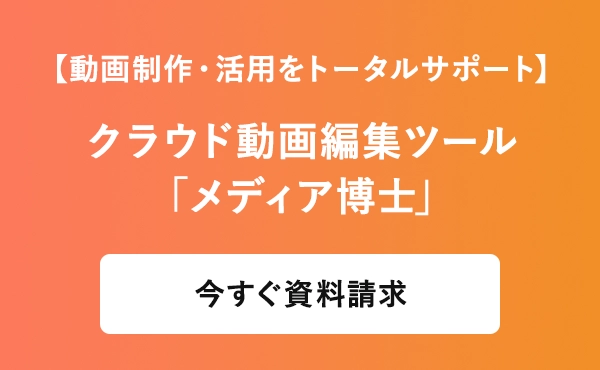新人教育に動画マニュアルを導入するメリットとマニュアル動画制作のポイント
2025-03-01
2024-01-30

動画マニュアル作成・管理ツールのご案内資料
今すぐ無料ダウンロードビジネスにおいて動画はさまざまなシーンで活用できますが、近年取り入れる企業が増えてきているのが新人教育用の「動画マニュアル」です。
動画マニュアルには紙のマニュアルにはないメリットがあるため、導入を検討されている企業も多いのではないでしょうか?
今回は、実際に新人教育に動画マニュアルを活用している企業の事例に触れながら、新人教育を動画マニュアルでおこなうメリットや動画マニュアルを作成する際に抑えておきたいポイントなどについて紹介していきます。
動画マニュアルには紙のマニュアルにはないメリットがあるため、導入を検討されている企業も多いのではないでしょうか?
今回は、実際に新人教育に動画マニュアルを活用している企業の事例に触れながら、新人教育を動画マニュアルでおこなうメリットや動画マニュアルを作成する際に抑えておきたいポイントなどについて紹介していきます。
目次
新人教育を動画マニュアルでおこなう3つのメリット
新人教育を動画マニュアルでおこなう場合、紙のマニュアルにはないさまざまなメリットが得れられるようになります。新人教育を動画マニュアルでおこなう3つのメリットについて解説していきます。
業務への理解度を高められる
新人教育に動画マニュアルを活用することで得られるメリットの中でも特に大きなメリットとしては、業務への理解度を高められる点があげられます。動画以外の業務マニュアルには紙のマニュアルやPDFなどのマニュアルがあげられますが、これらは、
・テキスト
・画像
・イラスト
テキストや画像、イラストでも十分にマニュアルとしては機能しますが、複雑な工程になるとどうしても伝わりづらくなってしまいがちです。
一方、動画マニュアルの場合だと、
・映像
・画像
・イラスト
・アニメーション
・音声
特に、ソフトなどのシステムの操作方法や機械の操作方法を解説する複雑な作業のマニュアルには動画での解説が最適です。
このように、動画マニュアルはさまざまな要素でマニュアルを構成し、伝えることができるため、業務への理解度をより高められるようになっています。
動画で学ぶためイメージしやすい
動画マニュアルには、作業内容をイメージしやすいというメリットもあります。紙やPDFなどのマニュアルの場合、先ほど紹介したように、
・テキスト
・画像
・イラスト
業務に携わったことのない新人社員は特にその傾向が強いと言えるでしょう。
一方、動画マニュアルの場合は実際に作業をおこなっている様子を映像として配信できるため、テキストや画像だけでは伝えづらい、イメージしてもらいづらい内容でもしっかりとイメージしてもらいながら落とし込んでもらうことができるようになっています。
コストを抑えられる
コストを抑えられるのも動画マニュアルの代表的なメリットの一つです。新人を特定の施設に集めて研修をおこなったり出張させて学ばせたりといった形で教育をおこなっている企業も多いかと思いますが、そういった形での教育にはとにかくコストがかかります。
これらの教育方法には、
・交流を深める
・現場で働きながら学べる
・疑問点をその場で質問できる
一方、動画マニュアルの場合だと、マニュアル制作にかかるコストを抑えながら、映像を通してよりリアルな形で学ぶことができます。
実際にその場で集まって学ぶ研修と比較すると学習効果は見劣りしてしまいますが、コストパフォーマンスの高さを考えると非常に魅力的な研修方法だと言えるでしょう。
新人教育を動画マニュアルでおこなう3つのデメリット
動画マニュアルは新人教育において非常に有効なツールですが、導入に際してはデメリットも理解しておく必要があります。新人教育を動画マニュアルでおこなう3つのデメリットとその解決方法について解説していきます。
制作や更新に時間がかかる
動画マニュアルの最大の課題は、制作や更新に時間がかかることです。テキストやPDFのマニュアルであれば、必要な箇所だけを修正してすぐに更新できますが、動画の場合は撮影や編集などの工程が必要となるため、簡単に修正できません。特に、業務の手順や社内ルールが頻繁に変わる場合、その都度動画を撮り直す必要があり、更新の負担が大きくなります。
この課題を解決するためには、短い動画を複数作成し、必要な部分だけを更新する方法が有効です。
また、ナレーションやテキストを後から変更できる編集ツールを活用することで、大幅な撮り直しをせずに修正をおこなうことができます。
細かい質問や個別対応が難しい
動画マニュアルは、一方的に情報を提供する形式であるため、新人が不明点を抱えた際にすぐに質問できないという課題があります。紙のマニュアルや対面の研修であれば、指導者に直接質問して疑問を解消できますが、動画ではその場でのやり取りができません。そのため、動画マニュアルを視聴しても、疑問が残ったままになり、業務の理解が十分に進まないことがあります。
この課題を解決するためには、動画マニュアルだけでなく、補足のサポート体制を整えることが重要です。
例えば、社内チャットツールやオンラインQ&Aのプラットフォームを活用し、新人が疑問点を投稿できるようにすると、効率的に問題を解決できます。
一方的な学習になりやすい
動画マニュアルは、視聴者が受け身の状態で学ぶことになるため、一方的な学習になりがちです。特に、実践的なスキルを身につける必要がある業務では、動画を見るだけでは知識の定着が十分でない場合があります。実際に手を動かして作業を行うことで習得できる技術や、現場での対応力が求められる業務においては、動画の視聴だけでは不十分です。
この課題を解決するためには、動画マニュアルの視聴後に実践型のトレーニングを組み合わせることが効果的です。
例えば、動画を見た後に実際の業務を体験する機会を設けたり、クイズ形式の確認テストを行ったりすることで、知識の定着を促すことができます。
新人教育用に動画マニュアルを制作する上で抑えておきたい3つのポイント
実際に新人教育用の動画マニュアルを制作する場合、・画面収録機能などを有効活用する
・音声や映像の質にこだわる
・動画の強みを活かす
これらのポイントを無視して動画マニュアルを作ってしまうと、動画の強みを活かせないマニュアルができあがってしまいかねません。
それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。
体系的に学べるようにする
動画マニュアルを制作する場合、マニュアルの内容にもよりますが、なるべく体系的に学べるものを制作するようにしましょう。本のように体系的に少しずつステップアップして学べるような形式にしておけば、次に何をすればいいか迷ってしまうことがありません。
学習の順番を自分で組み立てなくても用意された順番にそって動画を確認していけば学べるようになっているため、効率的に学習を勧めることができるようになります。
音声や映像の質にこだわる
動画マニュアルを制作する場合、内容だけでなく音声や映像の質にもこだわるようにしましょう。いくらマニュアルの内容が良くても、音声や映像の質が悪いと学習効果は半減してしまいます。
何より、新人の「学びたい」という意欲を低下させてしまいかねませんので、しっかりと見れるレベルの音声や映像でマニュアルを制作するようにしてください。
動画の強みを活かす
動画マニュアルを制作する場合、動画の強みを活かすことを意識してマニュアルを制作するようにしましょう。当たり前に聞こえるかもしれませんが、動画マニュアルを音声や画像だけで制作する企業は少なくありません。
それだと紙のマニュアルやPDFなどでのマニュアルとほぼ変わりません。
そのため、紙のマニュアルやPDFなどでのマニュアルにはない、
・映像
・音声
・アニメーション
新人教育に動画マニュアルを活用している企業の事例3選
動画マニュアルを制作する場合、参考にしたいのが、実際に動画マニュアルを取り入れている企業の事例です。動画マニュアルを制作する上で参考になる3つの事例を紹介していきます。
NYNY
関西を中心に美容室を展開している「NYNY」。
NYNYでは、カットの方法など技術的な内容から電話の応対方法までを動画でマニュアル化し、YouTubeに公開しています。
こちらの動画は電話応対に関するマニュアルですが、映像とテキストを駆使した、非常にわかりやすい動画マニュアルとなっています。
結チャンネル
近畿生コン関連協議会が業界で働く方向けに動画マニュアルを公開しているYouTubeチャンネル、「結チャンネル」。
こちらのチャンネルでは、トラックの誘導の仕方から運搬、荷降ろしまで、生コン業界で働く新人が学べる動画を多数公開しています。
こちらの動画は生コンワーカーの1日の大まかな流れを紹介する動画マニュアルで、これからこの業界で働くにあたり、どういった流れで業務にあたればいいのかがイメージできる良質な動画マニュアルとなっています。
博多久松

おせち料理の製造・販売をおこなっている「博多久松」。
博多久松も、YouTubeチャンネルで動画マニュアルを公開しています。
こちらの動画は工場に勤務するスタッフに向けたもので、工場内での勤務の仕方について丁寧に解説されています。
最近増えてきている外国人労働者への対応も考慮し、英語の字幕がそえられている点にも注目です。
外国人労働者の受け入れを検討している、あるいはすでに受け入れている企業は、ぜひ参考にしたい事例だと言えるでしょう。
まとめ
実際に動画マニュアルを取り入れている企業の事例をまじえながら、動画マニュアルを取り入れるメリットやマニュアルを制作する際に抑えておきたいポイントなどについて紹介してきました。動画マニュアルは、
・業務への理解度を高められる
・動画で学ぶためイメージしやすい
・コストを抑えられる
・時間や場所を選ばず学ぶことができる
制作するのに時間がかかるというデメリットもありますが、長期的な視点で見ればデメリットよりもメリットの方が大きいと言えるので、気になっている方はぜひ取り入れられてみてはいかがでしょうか?
実際に取り組む際は、今回紹介した3つの事例が非常に参考になりますので、ぜひ参考にしながら取り組んでみてください。
マニュアルの作成・共有・発信で社内業務をDX化
【マニュアル博士】
クラウド動画制作ツールでマニュアル動画をカンタン作成
クラウド動画作成ツールのマニュアル博士ならブランディング動画・プロモーション動画・社内広報動画・広告動画などを簡単制作!
誰でも作れる・すぐに作れる・いくらでも作れる
マニュアル博士での動画作成には、難しい操作や知識は必要ありません。初心者でも手間なく短時間で完成させることができAI機能や専属コンサルタントが動画作成をサポートします。
また、定額プランで月に何本作ってもOK!いつでも更新・アップロードができます。

 マニュアル活用をお考えの方
マニュアル活用をお考えの方