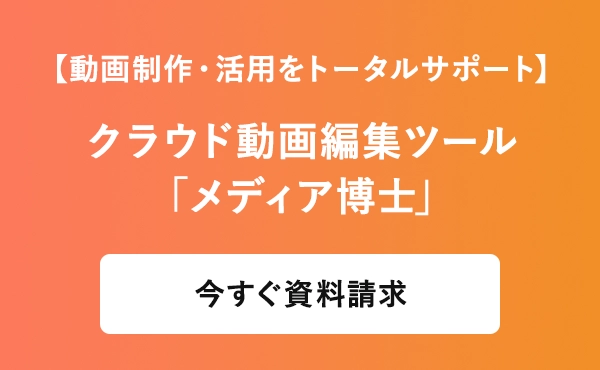KY活動(危機予知活動)とは何をする?進め方や具体的な活動を紹介!
2025-04-26
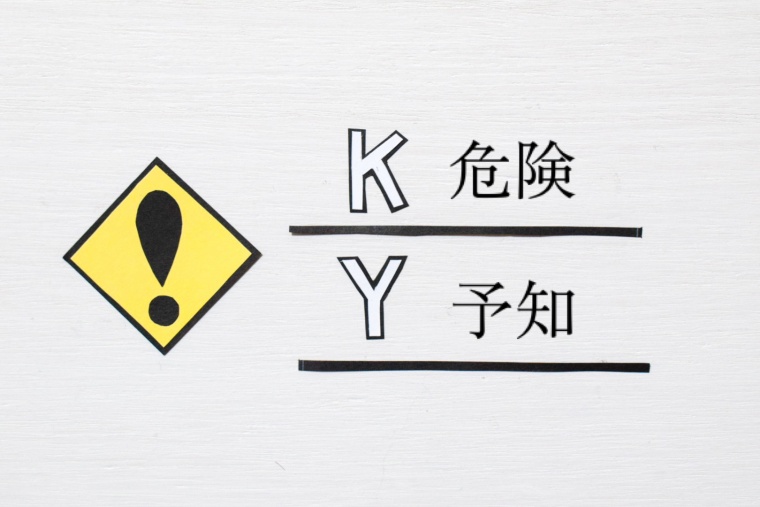
動画マニュアル作成・管理ツールのご案内資料
今すぐ無料ダウンロード作業現場など、職務を遂行するにあたって、意識しなければケガや労災につながることがあります。そのような事態を防ぐため、KY活動の実施が重要視されていますが、KY活動とはどのように進めればよいでしょうか。
そこで本章では、KY活動とは何か、その進め方や、取り組んでいく中で起こる問題と解決法などを紹介します。KY活動について詳しく知りたい方や、実施したいと思っている方は必見です。
そこで本章では、KY活動とは何か、その進め方や、取り組んでいく中で起こる問題と解決法などを紹介します。KY活動について詳しく知りたい方や、実施したいと思っている方は必見です。
目次
KY活動(危険予知活動)とは?
KY活動(危険予知活動)とは、職場や作業現場で、従業員が日常的に危険を予測し、事前に対策を講じる活動です。主に現場の従業員が積極的に参加し、日常業務の中で様々な危険や安全上の問題を見つけ出し、改善策を考案していきます。KY活動をすることで、事故や災害を未然に防ぎ、安全な職場環境の維持と向上が期待できます。KY活動は定期的に行われることが望ましく、従業員の危機意識を高め、職場全体での安全管理の意識と取り組みが促進されます。
リスクアセスメントと何が違うか
危険予知活動と似た言葉でリスクアセスメントという言葉があります。リスクアセスメントとは、職場のリスクを定量的に評価し、対策の優先度を決定して、危険な機械設備や物質を除去・低減する「ハードとソフト面の両方を含む総合的な取り組み」です。リスクアセスメントでは、マニュアル作成や保護具の設置などを含め、管理者や経営層も関与して労働災害を防止します。一方、KY活動は、作業者が日々の作業中に危険を予測し、リスクを回避する「ソフト面」の対策だという点が異なります。
KYサイクルとは
KY活動は、日々の安全活動として業務に組み込めると理想的です。毎日の業務に取り入れる考え方をKYサイクルといいます。具体的には、一日を「業務前」「業務中」「業務後」の3つに分け、安全活動を組み入れていきます。例えば、業務前には点検整備や業務指示、業務中には指差し呼称などの安全確認、業務後には清掃点検や報告をするなどが該当します。日々の活動に組み込み、自然に安全管理できるようにするのがKYサイクルです。
KY活動(危険予知活動)の進め方
KY活動(危険予知活動)の効果的な進め方について説明します。KY活動は、従業員の安全意識を高め、問題解決能力を向上させるために「基礎4R法」を活用して実施します。この方法は繰り返し行うことで、従業員が危険を早期に認識し、適切な対策を講じる力を養うことができます。以下に、具体的な進め方を示します。
1ラウンド:現状確認
最初のステップでは、職場や現場のリスクを洗い出します。従業員同士で情報を共有し、あらゆる危険要因をリストアップします。ここでは、危険の規模に関わらず、多角的な視点でリスクを捉えることが重要です。できるだけ多くの従業員を巻き込み、意見を交換してリスクの全体像を把握します。
2ラウンド:本質の追及
次に、洗い出した危険がなぜ危険なのか、理由を深掘りします。特に重要なリスクを選定し、そのリスクがどのように危険に繋がるのかを明確にします。従業員間で議論を交わし、危険の本質をしっかりと理解することで、次のステップでより効果的な対策を立案します。
3ラウンド:対策の策定
このラウンドでは、認識した危険に対する具体的な対策を立てます。対策を立案する際は、実行可能で具体的な提案を目指します。従業員全員が意見を出し合い、複数の対策案を挙げます。「どのような方法でその危険に対処できますか?」という質問を使って、具体的な解決策を模索します。対策案は一つに絞る必要はなく、次のステップで優先順位を決め、最も効果的な行動計画を定めます。
4ラウンド:行動目標の設定
最後に、策定した対策を基に具体的な行動目標を設定します。最も優先すべき対策や、実施が必須の項目を明確にした後、従業員それぞれが実行すべき行動を具体的に決定します。例えば、「作業前に安全装置の確認を行う」といった、具体的な目標設定を行い、危険を防ぐために必要な行動を明確に定めます。
この4つのラウンドを繰り返すことで、従業員は危険を予測し、適切な対策を講じる力を身につけることができます。
KY活動のネタ切れ問題の背景と対策
KY活動の問題点として、「ネタ切れ問題」が指摘されます。ネタ切れ問題とは、初期段階では多くの危険項目が挙がりますが、それらに対する対策を進めるうちに明確な危険が減少し、新たな危険が見つけにくくなることを指します。これが原因で、KY活動が単調化されたり、実施されなくなる場合があります。
KY活動でネタ切れの問題が発生する背景
KY活動でネタ切れの問題が発生する背景には、いくつかの要因があります。初期には多くの危険や改善点が見つかりますが、時間が経つと従業員の意識が鈍化し、同じような問題が繰り返し挙がることがあります。また、繰り返し対策を講じることで、初期の危険や改善点が解決され、新たな問題の発見が難しくなる傾向もあります。
さらに、従業員間での危機意識や安全への取り組み姿勢に差が生じ、積極性に差がでると、全体的なネタ切れに拍車をかけることがあります。従業員の危機意識が活動の質を左右するため、注意が必要です。
KY活動でネタ切れを防止するためには
KY活動のネタ切れを解消する方法として、以下の3つのアプローチが効果的です。これらの方法を組み合わせて実践することで、KY活動の質と効果を高めつつネタ切れを防げます。日常の問題点に敏感になる
日常業務の中で、小さなヒヤリハットや問題点を見逃さず、具体的に捉えることが重要です。例えば、製造現場では機械の異音や部品の不良といった些細な異常が、大きな事故の前兆となることがあります。早期警戒が、リスクの発見につながります。
問題点を細分化し追及する
さらに、問題点を深堀りして具体化し、「なぜ?」を追求することが重要です。例えば、顧客からの苦情があった場合、その背景にあるループホールやコミュニケーション不足など、根本原因を明らかにすることで再発防止策を講じることができます。
問題点は報告しやすい文化を醸成する
報告しやすい文化を育てることも不可欠です。従業員が安心して問題を報告できる環境を整えるためには、匿名報告の導入や報奨制度の設定などが有効です。例えば、ITセキュリティ分野では、フィッシング詐欺の被害を報告した社員に対して、特別な表彰やインセンティブを与えることで、報告意欲を高めています。
まとめ
本記事では、KY活動(危機予知活動)とは何かを解説しました。KY活動は、職場での危険を予測し、事前に対策を講じる取り組みであり、従業員の参加と日常業務での問題点発見が大切です。本記事の内容を、ぜひ職場でも活用してみてください。
マニュアルの作成・共有・発信で社内業務をDX化
【マニュアル博士】
クラウド動画制作ツールでマニュアル動画をカンタン作成
クラウド動画作成ツールのマニュアル博士ならブランディング動画・プロモーション動画・社内広報動画・広告動画などを簡単制作!
誰でも作れる・すぐに作れる・いくらでも作れる
マニュアル博士での動画作成には、難しい操作や知識は必要ありません。初心者でも手間なく短時間で完成させることができAI機能や専属コンサルタントが動画作成をサポートします。
また、定額プランで月に何本作ってもOK!いつでも更新・アップロードができます。

 マニュアル活用をお考えの方
マニュアル活用をお考えの方