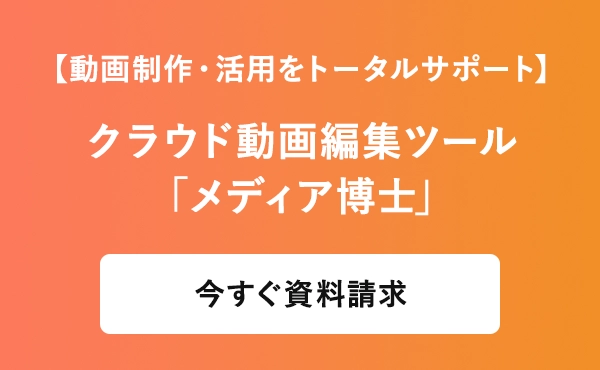マニュアルをつくりたい企業必見!マニュアルの作成方法を6つの手順で徹底解説
2025-02-28
2024-01-24

動画マニュアル作成・管理ツールのご案内資料
今すぐ無料ダウンロード企業が社員を育てていく上で欠かせない「マニュアル」。
マニュアルを用意しない状態での育成は非効率になってしまいがちですし、教える人によって伝え方が異なるなどのトラブルも引き起こしてしまいかねません。
実際、マニュアルの必要性や重要性を感じ、マニュアル作成に取り組みたいと考えている企業も多いのではないでしょうか?
今回は、「マニュアルをつくりたい」と考えている企業向けに、マニュアルの作成方法について解説していきます。
マニュアルを用意しない状態での育成は非効率になってしまいがちですし、教える人によって伝え方が異なるなどのトラブルも引き起こしてしまいかねません。
実際、マニュアルの必要性や重要性を感じ、マニュアル作成に取り組みたいと考えている企業も多いのではないでしょうか?
今回は、「マニュアルをつくりたい」と考えている企業向けに、マニュアルの作成方法について解説していきます。
目次
マニュアルを作成する目的
企業が業務を円滑に進めるためには、統一された基準が必要です。その基準を明確にし、誰でも同じ手順で作業できるようにするために、マニュアルは欠かせません。ここでは、マニュアル作成の目的について詳しく解説します。業務の標準化
業務の標準化とは、作業の手順やルールを統一し、誰が業務を担当しても一定の品質を維持できるようにすることです。統一された手順がなければ、社員ごとに作業の進め方が異なり、効率が低下し、品質にもばらつきが生じます。例えば、営業活動で提案資料の作り方が統一されていなければ、成果物に差が出てしまいます。マニュアルを作成し、基準を設けることで、全社員が同じ手順で業務を遂行でき、無駄な作業を減らせます。
動画マニュアルを活用すれば、視覚的に業務の流れを理解しやすくなります。
新入社員や異動者のスムーズな教育
新入社員や異動者が業務を習得するには時間がかかります。教育担当者の説明だけでは、伝える内容にばらつきが出ることがあり、理解度にも差が生じる可能性があります。マニュアルがあれば、業務の流れを体系的に学べ、スムーズに適応できるようになります。
特に動画マニュアルを活用すれば、作業の実例を視覚的に確認できるため、より直感的に理解しやすくなります。教育担当者の負担を軽減し、効率的な教育が可能になるのもメリットです。
属人化の防止
業務が特定の社員に依存する状態を防ぐためにも、マニュアルは必要です。特定の人しか業務の詳細を知らない場合、その人が休職や退職すると業務が滞るリスクが高まります。マニュアルがあれば、業務の引き継ぎがスムーズに行え、急な異動や退職にも対応しやすくなります。業務の透明性が向上し、誰でも同じクオリティで業務を遂行できる環境が整います。
動画マニュアルを活用すれば、実際の作業を記録し、スムーズな継承が可能になります。
品質を一定に保つ
製造業やサービス業では、業務の品質を一定に保つことが重要です。例えば、製造工程が標準化されていなければ、製品の仕上がりにばらつきが生じます。サービス業でも、接客対応に差があると顧客満足度の低下につながります。
マニュアルを整備し、業務の流れや基準を明確にすることで、全社員が同じ手順で作業できる環境を整えられます。
特に、実際の動作が求められる業務では、文章だけでなく動画を活用することで、より分かりやすく情報を伝えられます。
マニュアルを作成するときの流れ
マニュアルを作成する場合、主に以下のような流れで作成していくことになります。1.どの作成方法でマニュアルつくりを進めるかを決める
2.マニュアルを作成する目的を明確にする
3.構成を作る
4.フォーマットを作る
5.構成とフォーマットに沿ってマニュアルを作る
6.フィードバックを集めて改善する
どの作成方法でマニュアルつくりを進めるかを決める
「マニュアル」と聞くと紙のマニュアルをイメージする方が多いかと思いますが、他にもデジタルマニュアルや動画マニュアルなど、いくつか種類があります。マニュアルつくりに取り組む場合、まずはどの作成方法でマニュアルを作成するかを決めなくてはいけません。
紙のマニュアル
マニュアルの作成方法の中で定番の方法と言えるのが、紙のマニュアルです。市販の製品を購入したときについてくる説明書も、紙のマニュアルにあたります。
最もなじみのあるマニュアルなので、取り入れやすかったり活用しやすいというメリットがあります。
一方、マニュアルにボリュームが出てくると必要な情報を探すのが難しくなってしまいがちですし、持ち運びしにくいというデメリットがあるため注意しなくてはいけません。
また、印刷するたびにコストが発生するため、長い目で見るとコストパフォーマンスの悪いマニュアルの作成方法だと言えます。
デジタルマニュアル
近年紙のマニュアルの代わりに取り入れる企業が増えてきているのが、パソコンなどのデジタルデバイスで確認できるデジタルマニュアルです。パワーポイントなどの資料作成ツールでマニュアルを作成し、PDF形式で保存するなどして活用していきます。
閲覧するのにデバイスが必要になるというデメリットこそあるものの、印刷する必要がありませんし、情報を探しやすいというメリットがあります。
また、紙のようにかさばらないため、保管場所に困ることもありません。
動画マニュアル
紙のマニュアルやデジタルマニュアルはテキストや画像で構成されるため、機械の操作方法やツールの操作方法など、細かな手順を伝えるのに向いていません。その弱点を補ってくれるのが、動画マニュアルです。
動画マニュアルは映像を通して解説できるため、細かな手順が伝わりやすく、機械やツールの操作方法を解説するマニュアルとして大活躍してくれます。
作成するのに手間がかかるという側面はありますが、イチオシのマニュアルの作成方法だと言えるでしょう。
マニュアルを作成する目的を明確にする
マニュアルの作成方法を決めたら、次にマニュアルを作成する目的を明確にしていきます。・新入社員の教育のため
・ノウハウを共有するため
・製品やツールの正しい使い方を把握してもらうため
内容がブレてしまうと本来の意図と異なる仕上がりになり、マニュアルを作成した意味がなくなってしまう可能性があるため、事前に「何のためにマニュアルを作成するのか」を明確にしておく必要があります。
構成を作る
マニュアルを作成する目的が明確になったら、いきなりマニュアルを作り始めるのではなく、まずは構成を作っていきます。構成は、マニュアルで解説する内容の順序を決める作業です。
軽視されてしまいがちですが、「マニュアルの使いやすさは構成によって決まる」と言っても過言ではありません。
製品やツールの使用方法について解説するマニュアルであれば具体的な操作の手順が決まっているためそこまで構成の重要性は高くありません。
一方、その他のマニュアルの場合、どの情報をどの順番で読み手に提供するかで内容の理解度が大きく異なってきます。
マーケティングの知識を持ち合わせていない未経験者にマーケティングの必要性や考え方、具体的な取り組み方について解説するマニュアルを作成するとしましょう。
その場合、いきなり具体的なマーケティングの手順や取り組み方について解説しても頭に入ってきません。
なぜなら、マーケティングの必要性やマーケティングに対する考え方など、本質の部分を理解できていないからです。
そのため、この場合は、マーケティングの概要や必要性、マーケティングを展開していく上での考え方などについて解説し、その上で具体的な進め方や方法について解説していく方が良いと言えます。
このように、マニュアルつくりにおいて構成は非常に重要な工程であるため、マニュアルの作成をスタートさせる前に構成を作り込んでおく必要があるわけです。
フォーマットを作る
構成ができたら、後は各項目で伝えたいことを文字や画像、映像で伝えていくだけですが、情報を伝える際のフォーマットが統一されていないとマニュアルを使用する側が混乱してしまいかねません。また、フォーマットを用意せず、その都度一から作成してしまっていてはいくら時間があっても足りません。
フォーマットはマニュアル作成の効率化にもつながるので、事前に作成し、用意しておくようにしましょう。
構成とフォーマットに沿ってマニュアルを作る
構成とフォーマットができたら、その構成とフォーマットに沿ってマニュアルつくりを進めていきましょう。マニュアル作成は大変な作業ですが、構成とフォーマットがしっかりとしていれば、作業自体はスムーズに進められるはずです。
マニュアルを作るときは、
・どうすればより相手に伝わりやすくなるか
・どうすればより相手が理解しやすくなるか
フィードバックを集めて改善する
マニュアルは、一度作って終わりではありません。公開した後は、社員からフィードバックを集め、その内容を元にして改善をしていかなくてはいけません。
どれだけマニュアルを作るのに長けている人でも、最初から完璧なマニュアルを作ることはできません。
必要な情報が入っていないこともあれば、逆にそれほど重要ではない情報を詰め込んでしまっているケースもあります。
また、情報を伝える順序である構成の段階からダメ出しが入ることもあるでしょう。
せっかく作成したマニュアルを修正したり作り直したりするのは面倒かもしれませんが、現場が使いやすいと感じるマニュアルこそ良いマニュアルだと言えるので、現場の声を聞きながら改善を繰り返し、より洗練されたマニュアルに仕上げていきましょう。
まとめ
マニュアルの重要性や必要性を感じ、「マニュアルをつくりたい」と考えている企業向けに、具体的なマニュアルの作成方法について紹介してきました。マニュアルの作成は、どれだけ丁寧に準備できるかによって質が決まると言っても過言ではありません。
計画を立てず闇雲にスタートさせても良いマニュアルはできませんし、構成やフォーマットを用意しない状態で取り組んでしまっていては時間がいくらあっても足りません。
今回紹介した流れに沿って、少しずつ形にしていくことを意識しながら制作することが大切です。
まずは、
・紙
・デジタル
・動画
マニュアルの作成・共有・発信で社内業務をDX化
【マニュアル博士】
クラウド動画制作ツールでマニュアル動画をカンタン作成
クラウド動画作成ツールのマニュアル博士ならブランディング動画・プロモーション動画・社内広報動画・広告動画などを簡単制作!
誰でも作れる・すぐに作れる・いくらでも作れる
マニュアル博士での動画作成には、難しい操作や知識は必要ありません。初心者でも手間なく短時間で完成させることができAI機能や専属コンサルタントが動画作成をサポートします。
また、定額プランで月に何本作ってもOK!いつでも更新・アップロードができます。


 マニュアル活用をお考えの方
マニュアル活用をお考えの方