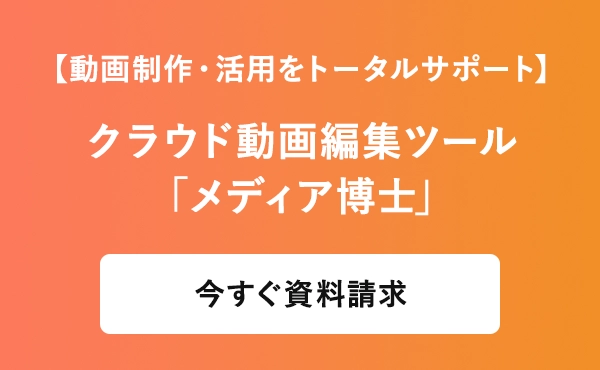品質管理の4Mとは?実施の目的とそれぞれの意味や分析の仕方を解説

動画マニュアル作成・管理ツールのご案内資料
今すぐ無料ダウンロードそこで本記事では、品質管理の4Mとは何か、実施の目的とそれぞれの意味や分析の仕方を解説していきます。よりよく問題解決をしたい方は是非参考にされてみてください。
4Mとは
4Mとは、製造業やプロジェクト管理分野でよく使われる用語で、物事を次の4つの要素でとらえる手法を指します。4つの要素は以下で、「M」はそれぞれの用語の頭文字をとっています。1. Man(人)
2. Machine(機械)
3. Material(材料)
4. Method(方法)
続いて、それぞれの要素と、何に影響を与えるかについて説明します。
Man(人)
Manは、作業者や管理者などの人間要素を指します。人の技能や訓練、モチベーションなどが製品の品質や生産性に直接影響を与えます。業務では具体的に、以下のような点に影響をもたらします。・従業員の技能や知識の不足
・新人や経験不足の作業者によるミス
・コミュニケーション不足による誤解や問題
Manの分析では、従業員の教育・訓練プログラムの改善、適切な業務指導やフィードバックの提供、チームワークやコミュニケーションの促進が考慮されます。
Machine(機械)
Machineは、製造プロセスにおける機械や設備、工具などの要素を指します。機械の正確性や性能が製品の品質に直結します。業務では具体的に、以下のような点に影響をもたらします。・機械のメンテナンス不良による故障や品質低下
・操作方法の習熟度不足による誤操作
・製造装置の老朽化や技術的限界
Machineの分析では、定期的なメンテナンススケジュールの見直し、新しい技術や装置の導入、操作手順の改善が考慮されます。
Material(材料)
Materialは、製品を作るための原材料や部品を指します。資材の品質や供給の安定性が、製品の最終品質に大きく影響します。業務では具体的に、以下のような点に影響をもたらします。・資材の品質が不安定であることによる製品のばらつき
・新しい供給業者との調整不足による納期の遅れ
・環境変動による資材の品質変化
Materialの分析では、供給業者との品質管理の協定の見直し、代替資材の検討、品質管理の強化が考慮されます。
Method(方法)
Methodは、製造プロセスや作業手順、品質管理の方法論を指します。効率的で品質の高い製造プロセスが確立されているかどうかが重要です。業務では具体的に、以下のような点に影響をもたらします。・作業手順の不適切さによるミスや廃棄物の増加
・生産ラインの効率が低いことによる生産性の低下
・品質管理の手法が不適切であることによる不良品の増加
Methodの分析では、作業手順の見直しや標準化、生産ラインのレイアウトの最適化、品質管理システムの改善が考慮されます。
これらの要素が、製品の品質や生産効率に大きな影響を与えるととらえ、管理や改善の対象になります。例えば、生産ラインで問題が発生した場合、4Mの観点にわけて原因を特定することで、適切な対策を講じることができると考えられます。
製造業と物流業における4Mの違い
4Mは、製造業と物流業の両方で活用される品質管理のフレームワークですが、それぞれの業界での適用方法には違いがあります。製造業では、4Mは生産工程の品質向上や生産効率の最適化を目的として活用されます。
例えば、Man(人)の要素では、作業員のスキル向上やマニュアルの徹底が重要視され、Machine(機械)では、生産設備の定期メンテナンスや自動化システムの導入が品質向上の鍵となります。
一方、物流業では、4Mは配送の効率化や安全管理の強化に重点を置いて適用されます。
Man(人)の要素では、ドライバーや倉庫スタッフの教育や適切な労働環境の整備が重要となります。Machine(機械)は、トラックやフォークリフトなどの輸送機器の保守管理に関連し、老朽化や故障が配送の遅延や事故につながるリスクを含んでいます。
また、Material(材料)の観点では、製造業では原材料の品質管理が中心になりますが、物流業では輸送する商品の梱包や保管環境が問題の対象になります。
例えば、食品や医薬品の輸送では、適切な温度管理が求められます。Method(方法)の違いとしては、製造業では生産ラインの工程改善が主な焦点になるのに対し、物流業では配送ルートの最適化や在庫管理の効率化が重要視されます。
4Mと5M+1Eや6Mとの違い
4Mは基本的な分析手法ですが、より詳細な品質管理を行う場合には、5M+1Eや6Mといった視点を取り入れることで、より包括的な改善策を検討できます。4Mと5M+1Eとの違い
5M+1Eは、4MにMeasurement(測定)を追加し、さらにEnvironment(環境)を加えたものです。Measurement(測定)は、品質のばらつきを管理するために重要な要素で、製品の寸法や重量を適切に測定できなければ、品質基準を満たしているか判断できません。測定機器の精度やキャリブレーション(校正)も管理のポイントになります。
Environment(環境)は、作業環境や気温、湿度、騒音、照明などが製造プロセスや品質に与える影響を指します。例えば、電子部品の製造では静電気対策が必要になるなど、環境要因が品質に直接関わる場面は多くあります。
4Mと6Mとの違い
6Mは、4MにMeasurement(測定)を加えた5Mに、さらにManagement(管理)を加えたものです。Management(管理)は、組織の方針や経営戦略、ルールの整備、マネジメントの適切さが品質に与える影響を示します。
例えば、業務プロセスが適切に標準化されていなければ、従業員が個々の判断で作業を行い、品質のばらつきが発生する可能性があります。また、管理体制が不十分だと、適切な品質チェックが行われず、問題が発生しても迅速な対応ができません。
4Mの目的
4Mの要素はわかりましたが、なぜ4Mが重要なのでしょうか。4Mによる品質管理の主な目的は、製品の品質を向上させ、顧客満足度を高めることにあります。製品の製造に関わる人(Man)、機械(Machine)、材料(Material)、方法(Method)の各要素を徹底的に分析することで、抜け漏れなく問題点や改善点を洗い出せます。
さらに、品質管理を通じて無駄な作業やコストを削減し、製造コストを効率化できます。生産性の向上や安全性の確保は、企業全体の競争力を高めるための基盤を築きます。
4M分析の仕方
4M分析は、問題解決や事故発生時の原因究明に役立つツールです。ここでは、「自動車製造工場にて「塗装工程で塗装ムラが発生した」という問題を具体例に、4M分析の仕方を解説します。1. 問題の明確化
まずは、問題を明確にします。例えば、「塗装工程で完成車に塗装ムラが発生し、これにより、製品の見栄えが悪くなり、品質基準を満たさない車両が増えている」点が問題だとします。2. 因果関係の特定
続いて、問題の原因を探るために、4M(人、機械、材料、方法)の観点から分析を行っていきます。それぞれの観点で分析を行うと以下のようになりました。人 (Man)の観点
・新入社員が増え、経験不足の作業者が多いという、作業者のスキル不足 。
・塗装の技術に関する研修が十分に行われていないという、トレーニング不足。
機械 (Machine)
・スプレーガンのノズルが詰まっていることが多いという、スプレーガンの故障 。
・定期的なメンテナンスが行われておらず、塗装機械の調整が不十分という、設備のメンテナンス不足。
材料 (Material)
・使用している塗料のロットによって品質にばらつきがあるという、塗料の品質問題 。
・塗料の保管環境が適切でないため、塗料の粘度が変化しているという、保管方法の問題。
方法 (Method)
・塗装工程の標準作業手順書が存在しない、または守られていないという、作業手順の不徹底。
・塗装工程での品質チェックが適切に行われていないという、プロセス管理の不備。
3. データ収集と分析
各要素に関するデータが収集できたら、それぞれの要素に基づいて原因を詳しく分析していきます。例えば、作業者からの聞き取り調査を実施し、スキルやトレーニングの状況を確認したり、塗装機械の状態をチェックし、故障やメンテナンスの状況を把握するなどを行います。
4. 因果関係を考察し、改善策を立案・実施する
問題の原因と結果を分析し考察します。そして、分析結果に基づき、具体的な改善策を立案します。もし、作業者のスキルが問題なら、塗装技術に関する定期的なトレーニングを実施したり、設備が問題ならスプレーガンや塗装機械の定期メンテナンススケジュールを設定し、実施します。
5. 効果の検証と改善
改善策を実施した後は、その効果を検証します。品質をチェックしたり、作業者のフィードバック、設備の状態確認などは欠かせません。問題が解決された後も、継続的にモニタリングを行い適宜対応していきます。まとめ
本記事では、4Mとは何か、その実施方法も紹介しました。業務において、4M分析を活用すると、問題の原因を体系的に特定し、効果的な改善策が実施できます。ぜひ実践し、品質向上と、顧客満足度向上を実現させてください。
マニュアルの作成・共有・発信で社内業務をDX化
【マニュアル博士】
クラウド動画制作ツールでマニュアル動画をカンタン作成
クラウド動画作成ツールのマニュアル博士ならブランディング動画・プロモーション動画・社内広報動画・広告動画などを簡単制作!
誰でも作れる・すぐに作れる・いくらでも作れる
マニュアル博士での動画作成には、難しい操作や知識は必要ありません。初心者でも手間なく短時間で完成させることができAI機能や専属コンサルタントが動画作成をサポートします。
また、定額プランで月に何本作ってもOK!いつでも更新・アップロードができます。

 マニュアル活用をお考えの方
マニュアル活用をお考えの方